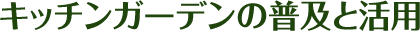5. キッチンガーデンの基礎知識 知っておきたい基礎用語
摘芯(ピンチ)・芽かき
茎の先端部を剪定することで、枝分かれや、生育を抑制したりする。若い側枝を芽摘み、芽かきともいう。トマト、ナスなどの果菜類では必ず行う。
わき芽
葉のつけ根などの節間部から出てくる芽で、腋芽ともいう。
畝立て・鞍築
露地において、野菜苗を育てるために、耕作した土を10〜20cm程度細長く盛り上げること。円型に盛り上げたものを鞍築(くらつき)という。
接ぎ木苗
連作障害や病害に強い台木に接ぎ木した苗で、トマトやナスキュウリなどをカボチャやカンピョウに接ぎ木して育てやすくしている。
親づる・子づる
つる性の野菜で、最初に伸びたつるで、親づるからわき芽で伸びたつるを子づるという。
筋まき(条まき)・直まき・ばらまき・点まき
種をまく方法。土の表面に棒などで浅く筋をつけ、ていねいに筋に沿ってまくことを筋まき。平らな土表面にまんべんなくまくことをばらまき。等間隔に穴をあけて、2〜3粒ずつまくことを点まきという。 ※葉菜類の種など細やかな種は、種をまく前日に水に浸しておくと発芽しやすくなる。
覆土
種まきをした後に土をかけること。水やりの際に、種が流亡するのを防ぐことにもなる。
連作障害
同じ場所で続けて同じ仲間の作物を育てる時、生育が悪くなり障害がでること。ナス科、ウリ科、マメ科などでよく起こる。
輪作
連作障害を避けるために、違う種類の作物を育てて繰り返し栽培していくこと。
天地返し・中耕
栽培終了後に表面の土と深い部分の土を入れ替えることで、栽培途中段階で、株間の土を軽く耕して空気を入れることを中耕という。
誘引
支柱、トレリス、ネットなどに、成長してきた茎やつる茎をひもで固定していくこと。目的に合った方向に伸ばし、転倒したりしないようにする。トマトやナスなどは結実していくと実が重たくなるので、分枝の節の下で誘引していく。
摘花・摘果・摘葉
花や果実の数を調整するために若い間に摘み取ること。トマトなど先に結実した実に栄養を集中させるために行う。ナスでは、結実した実の上にある葉を摘み取ることにより、風通しを良くし、実に傷をつけないようにする。あらかじめ残しておく花や葉、茎を決めてから行うように注意する。
早生・中生・晩生
種をまいてから収穫までの期間が短い品種を早生(わせ)、長いものを晩生(おくて)、中くらいのものを中生(なかて)という。
徒長
日光不足や温度、肥料のなどの影響により節間が間伸びしてしまうこと。苗を選ぶときには、株元がしっかりした本葉が元気なものを選びましょう。
本葉・子葉
発芽して最初に出た葉を子葉(ふたば)といい、その後に出た葉を本葉(ほんば)という。葉の形状が異なることがある。
間引き
種まきをして発芽した後に生育の旺盛な幼苗を残し、余分な苗を抜き取ること。種は多めにまくので、何段階かに分けて間引きを行う。ニンジン、ダイコン、ホウレンソウ、他葉菜類などの直まきする場合に間引きが必要。
鉢上げ
種まきトレーなどで発芽した幼苗をそのまま定植せずに、小さな鉢やポットに移し、植え替えすること。
土寄せ
作物が生長している途中で、株元に土を寄せて盛り上げること。株が倒れるのを防ぎ、根張りをよくするために行う。
遮光・雨よけ
作物の幼苗期に、強い直射日光から葉やけや乾燥から守るために行うこと。雨よけにもなり、苗を健全に生育させることにもなる。
嫌地(忌地)
土中に栄養分が偏ったり、連作によって微生物のバランスが崩れ作物の生育に悪影響をもたらすこと。
とうが立つ
葉菜類で花をつける生殖成長が始まり、花茎が伸びてくること。
つるぼけ
果菜類で肥料の与え過ぎなどにより、花芽分化をせずに葉や茎(つる)ばかりが生長してしまうこと。 ※大玉のトマトは、下から順番に実をつけていき、手の届く高さを超えるころに誘引したひもを解き、株元を中心に主枝をとぐろを巻くようにして、少しずつ全体の高さを下げていけば長期間多数の実を収穫できる。









1963年兵庫県生まれ。ガーデニングによる花と緑があふれるまちづくりを提唱し指導している。園芸肥料メーカー勤務を通し本格的に植物との関わりを持つ。90年に独立。ガーデニングコンサルタント会社・環境文化センターを設立し、現在に至る。家庭菜園を始める・続けるためのベストガイド『菜園生活パーフェクトブック』の監修・著。